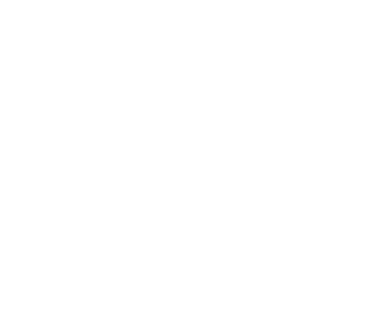【修了生インタビュー】サウンドデザイン領域10期修了生 伊東俊平さん
2025.08.27
 7月22日(火)、サウンドデザイン領域10期修了生 伊東俊平さんをお招きし、特別ゼミを行いました。伊東さんはNHK音響デザイン部に所属(2025年7月時点)され、現在放送中のNHK大河ドラマ『べらぼう』の音響デザインチームに参加されています。ゼミでは現在、整音中の1年夏期撮影実習作品の講評を頂き、映画専攻時代、そして、NHKの音響デザインでのお仕事を伺いました。
サウンドデザイン領域に入ったきっかけを簡単にお願いできますか。
7月22日(火)、サウンドデザイン領域10期修了生 伊東俊平さんをお招きし、特別ゼミを行いました。伊東さんはNHK音響デザイン部に所属(2025年7月時点)され、現在放送中のNHK大河ドラマ『べらぼう』の音響デザインチームに参加されています。ゼミでは現在、整音中の1年夏期撮影実習作品の講評を頂き、映画専攻時代、そして、NHKの音響デザインでのお仕事を伺いました。
サウンドデザイン領域に入ったきっかけを簡単にお願いできますか。
伊東 父親の趣味で家にオーディオセットがあって、幼い頃から音楽に興味を持っていました。それで、大学入試の時に「進路は音関係がいいな」と思って、日本大学芸術学部映画学科の撮影・録音コースに入学しました。そこから、僕の音響人生というものがなんとなくスタートしました。4年間、課題の制作を軸に音響のことをいろいろ自分なりに研究というか勉強しました。そして就活の時期になって「どうしようかなぁ〜」と思っていたところ、私と同じように日本大学芸術学部から映画専攻に入学していた先輩に話を聞いて、受験しようと思ったんです。映画専攻に入学されて2年間はいかがでしたか?
伊東 現場で音を録ってそれを仕上げに持っていくっていうのがすごく楽しくて・・・ 一番記憶に残っているのは、やっぱり修了制作の『タクシー野郎 昇天御免(川田真理監督)』ですね。タクシーの上でアクションするシーンがあって、本物のタクシーの上で川田監督とサウンドデザインの仲間を引き連れて、タクシーの上でひたすらアクションの音を録りまくるというのは大変でしたが楽しかったですね。『タクシー野郎 昇天御免』振り切れてやってましたね。
伊東 でも、もっと振り切りたかった。うーん・・・いろんなことを考えながらやったんですけど、結局、どう突き抜けていいかがわからないまま終わってしまったんですよ。・・・結局、技法というか技のことばっかり考えちゃうとか、サウンドデザインで何が本当に必要なのかっていうのを最後まで突き詰めて考えられてたか?と、今となっては思いますね。かなりタイトなスケジュールでしたね。
伊東 きつかったですけど、やっぱり現場が楽しかったですね。チームでやれること。 そしてみんな、上下関係もなく一緒に仲間としてここで勉強しながらいろんな意見交換しながら、時には喧嘩もしながらやっていく時間っていうのはこの先ないので。どうしても上下関係はあるし、それこそ発注元、予算のことみたいなことっていうのは、ここ(映画専攻)を出てしまったらずっとつきまとうので、そういうことがない中でサウンドに集中できたっていうのはすごくいい時間でした。今でもそういう時間欲しいなと思うぐらいのいい時間だったなという風に思います修了後、NHKに入局されました。最初から朝ドラ担当でしたか?
伊東 いやいや、最初の数年は色々やりましたよ。バラエティもやりましたね。バラエティなので音楽で番組をどんどん展開させていく手法は、映画専攻でやっていた音楽の使い方とは全く違うので大変でしたが、非常に勉強になりましたね。(他にも、22.2ch立体音響、ドキュメンタリーや歴史番組も担当。)その後、NHK大阪放送局配属になって、主だった番組としては2018年『まんぷく』、2021年『カムカムエヴリバディ』、2023年『ブギウギ』などドラマを担当することが多かったです。NHK音響デザインは選曲も担当するんですよね?
伊東 そうです。それも単純な選曲ではなくて、台本読んで「こういうシーンがあるのでこういう曲を書いてください」、「主人公のこういう心情を表す曲を書いてください」、「そのライバルの曲を書いてください」と、かなり具体的に作曲家に発注もしますし、納品された音楽データをパートごとに調整することもします。実質、音楽監督ですね。しかし同時に効果も担当するわけで、仕事量は多いですね。
伊東 多分、映画に落とし込んだら「音響の複数の仕事を一人でやっている」ということになるんでしょうけど、考えると映画専攻でやっていたことと変わらないですよね。変わってないっていうことが成立しているということはすごいと思いますし、サウンドデザイナーっていう職能が日本映画界にない現状の中、NHKではそういうことがすでに実践されてるということは、今後の日本映画界の音響の重要な指針となるものだと思います。 大阪から東京に戻られたのは去年2024年の4月ですね。
伊東 戻ってきて、BSの時代劇やオーディオドラマの音響効果を担当していましたが、ちょうど1年くらい前の夏に「大河ドラマ『べらぼう』に入ってくれ」っていう話をもらって、12月からMAが始まったので、それからずっと『べらぼう』な日々です。大変だと思いますが、やりがいのあるお仕事だと思いますし、充実した日々を送られていると感じます。最後に伊東さんが考える「サウンドデザイン」についてお聞かせ願えれば。
伊東 僕も本当にまだまだなんですけど、やっぱりサウンドデザイナーっていう仕事がどういうものであるべきかみたいなことは、学生時代から数えて15年弱やっていると考えるところではあって、それはつまり、全体的な音でどう演出していくかということだと思っています。言い換えると「その音が機能的であるか」を判断することなんだと思います。具体的に言えば「この音、この音楽がここから入ることによって、この機能を持つ」ということです。もちろん、個々の音の音質の良さも大事で音質が良いことによって選択肢は増えますが、そこが本質ではなくて最終的にトータルの音像がどう聴こえて物語に寄与するかを設計していくというのがサウンドデザイナーがなすべきことなのでは、と思っています。制作を進める中で自分が考える音のアイデアと意見が異なる人もいるかもしれないけど、やっぱり自分はこう思うんだっていう気概を持って仕事するのはすごく大事なことだと思います。映画専攻に来ている人は、多分自分がこうしたいとか自分がこれがいいと思ったことって何かしらはあるはず。何にもない状態でここには来てないはずなので、それをいかにうまく形にしていくか。出てきた編集に対して自分の持ってるセンス、何がいい、これがいい、これはダメっていうことをうまいこと差し込んでいくかみたいなのがいっぱいあると楽しいし、そういった試行錯誤を経ていいものができるんじゃないかなみたいな気はします。貴重なお話ありがとうございました。 (聞き手 サウンドデザイン領域教授 長嶌寛幸)
 伊東俊平
2014年に日本大学芸術学部映画学科を卒業後、サウンドデザイン領域10期生として入学。2016年に修了後
伊東俊平
2014年に日本大学芸術学部映画学科を卒業後、サウンドデザイン領域10期生として入学。2016年に修了後![]()